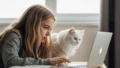うつ病と適応障害の主な違いは、原因の明確さと症状の持続期間にあります。
- 適応障害: 特定のストレス要因(例:職場や学校での人間関係、異動、引越しなど)によって引き起こされる一時的な心身の不調です。ストレスの原因から離れると症状が改善しやすいという特徴があります。症状は、ストレス要因に曝されてから3か月以内に現れ、ストレスがなくなると6か月以内に消失することが多いとされています。
- うつ病: 明確なストレス要因がない場合でも発症することがある精神疾患です。脳の機能的な変化が関係していると考えられており、環境が変わっても症状が長期間(2週間以上)続くことが特徴です。
症状の類似点と相違点
適応障害とうつ病は、抑うつ気分や意欲の低下、不眠、食欲不振など、似たような症状を呈することがあります。しかし、適応障害の症状は、その原因となるストレスから離れると軽減するか消える傾向があるのに対し、うつ病の症状はストレス要因とは関係なく持続します。
| 項目 | うつ病 | 適応障害 |
| 原因 | 特定の明確なストレス要因がない場合も多い。脳の機能的な変化が関係していると考えられている。 | 明確なストレス要因(例:人間関係、仕事、環境の変化)がある。 |
| 症状の出現 | ストレス要因に関係なく、じわじわと症状が現れることが多い。 | ストレス要因に曝されてから3か月以内に症状が現れる。 |
| 症状の特徴 | 抑うつ気分、興味・喜びの喪失、意欲の低下などが長期間(2週間以上)続く。ストレスの原因から離れても症状が改善しにくい。 | 抑うつ気分や不安、身体症状など、ストレスに対する過剰な反応として現れる。ストレスの原因から離れると症状が改善しやすい。 |
| 症状の持続期間 | 長期化する傾向がある。適切に治療しないと数か月から数年続くこともある。 | ストレス要因がなくなると、6か月以内に症状が消失することが多い。 |
| 治療 | 休養、薬物療法(抗うつ薬)、精神療法(認知行動療法など)が主体となる。 | 環境調整と休養が基本。必要に応じて薬物療法や精神療法が併用される。 |
| 診断 | DSM-5の診断基準に基づき、9つの主要な症状のうち5つ以上が2週間以上続くことなどが基準となる。 | ストレス要因が明確であり、そのストレスに対する反応が社会生活や職業生活に著しい支障をきたしていることが基準となる。 |
| 再発 | 適切な治療をしないと再発しやすい。 | ストレス要因が解消されれば再発のリスクは低いが、再び同様のストレスに曝されると再発することがある。 |
DSM-5に基づくうつ病の診断基準
診断には、以下の9つの症状のうち5つ以上が2週間以上にわたって存在し、かつそのうち少なくとも1つが**(1)抑うつ気分または(2)興味・喜びの喪失**である必要があります。
9つの主要な症状
| 症状番号 | 症状名 | 具体的な内容 |
| (1) | 抑うつ気分 | ほぼ一日中、ほとんど毎日、気分が沈んでいる、悲しい、虚しい、または絶望的だと感じること(他人から観察される場合も含む)。 |
| (2) | 興味・喜びの喪失 | ほぼ一日中、ほとんどの活動において、興味や喜びが著しく減退すること。 |
| (3) | 体重・食欲の変化 | 食事制限をしていないのに体重が著しく増減する(例:1ヶ月で5%以上)、または食欲が減退・亢進する。 |
| (4) | 睡眠障害 | ほぼ毎日の不眠(寝つきが悪い、途中で目が覚める、早朝覚醒など)または過眠。 |
| (5) | 精神運動性の焦燥または制止 | 落ち着きがなく動き回る(焦燥)か、動作や話し方が極端に遅くなる(制止)。これは本人だけでなく、他人から観察できるものであること。 |
| (6) | 疲労感または気力の減退 | ほぼ毎日、疲れやすさを感じたり、気力がなくなったりする。 |
| (7) | 無価値感または過剰な罪悪感 | ほとんど毎日、自分には価値がないと感じたり、不適切なほどの罪悪感を抱いたりする。 |
| (8) | 思考力・集中力の減退、決断困難 | 思考力や集中力が低下し、物事を決めることが難しくなる。 |
| (9) | 死についての反復思考 | 死について繰り返し考えたり、自殺を考えたり、自殺の計画を立てたりする。 |