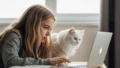「顧客リストの持ち出し」「社内ノウハウの私用PC保存」「新商品情報のSNS投稿」— 社員の守秘義務違反は、企業の存続を脅かす重大なリスクです。
社員の守秘義務は、個別の契約だけでなく、労働契約法上の誠実義務から当然に発生し、退職後も存続します。特に重要なのは、漏洩した情報を不正競争防止法上の「営業秘密」として保護できるかどうかです。なぜなら、この要件(秘密管理性・有用性・非公知性)を満たせば、企業は最大7年の懲役または700万円の罰金という刑事告訴を含む、強力な法的措置を取れるからです。しかし、企業側が「秘密管理性」を疎かにしていると、いざという時に法的に守られません。
1. 守秘義務の法的根拠
| 根拠 | 内容 | 対象となる情報 |
|---|---|---|
| 労働契約法第3条 | 誠実義務(信義則)から当然に守秘義務が発生 | 業務上知り得た全ての秘密 |
| 民法第709条・415条 | 不法行為・債務不履行による損害賠償責任 | 企業秘密全般 |
| 不正競争防止法第2条6項・第21条・22条 | 営業秘密の保護(刑事罰・民事措置あり) | 「営業秘密」(要件を満たすものに限る) |
| 就業規則・守秘義務契約 | 個別に定めた守秘義務 | 契約で指定された情報全般 |
| 個人情報保護法 | 個人情報の漏洩に対する責任 | 個人情報 |
2. 営業秘密として保護されるための3要件(不正競争防止法)
- 秘密管理性:秘密として管理していると客観的に認識できること
→ アクセス制限、パスワード、秘密指定の表示、誓約書など - 有用性:事業活動に有用な情報であること
- 非公知性:一般に知られていないこと
→ この3つを満たさない情報は「営業秘密」としては保護されないが、労働契約上の守秘義務は依然として残る。
3. 守秘義務違反となる典型例
| 行為 | 違反の該当性 |
|---|---|
| 顧客リストを退職時に持ち出す・競合他社に提供 | ◎(最も重い) |
| 社内の技術資料を私用PCに保存し、紛失 | ○ |
| SNSに「うちの新商品は○○だよ」と投稿 | ○ |
| 取引先との飲み会で「実はうちの原価率は…」と話す | ○ |
| 退職後に「前職ではこんなノウハウを使ってた」と競合で使う | ◎ |
| 家族に「今日○○社と大口契約取れた」と話す | △(内容による) |
4. 企業が取れる法的措置
| 措置 | 根拠 | 実務的な効果 |
|---|---|---|
| 民事訴訟(損害賠償請求) | 民法・不正競争防止法 | 実際に発生した損害+逸失利益を請求可能 |
| 差止請求・廃棄請求 | 不正競争防止法第3条・4条 | 情報の使用禁止、データ削除を強制 |
| 刑事告訴 | 不正競争防止法第21条(7年以下の懲役または700万円以下の罰金) | 悪質な場合に警察介入 |
| 懲戒解雇・懲戒処分 | 就業規則 | 即時解雇+退職金不支給が可能(判例多数) |
5. 実務でよく問題になるポイント
| 論点 | 判例・実務の傾向 |
|---|---|
| 退職後の守秘義務 | 原則として存続する(特に営業秘密・明確に指定された情報) |
| 在職中の私的利用(私用スマホでの撮影など) | 懲戒解雇が有効とされた例多数 |
| 「秘密指定がなかった」場合 | 営業秘密としては保護されないが、労働契約上の誠実義務違反として損害賠償・懲戒は可能 |
| SNSでの軽率な投稿 | 情報自体が営業秘密でなくても、懲戒解雇が有効(東京地裁平成30年など) |
| 競業避止義務との違い | 守秘義務は無期限に近いが、競業避止は合理的な範囲でしか拘束できない |
6. 企業がすべき予防策(実務必須)
- 入社時に個別の守秘義務契約を締結
- 重要情報に「秘密」「社外秘」の表示を徹底
- アクセス権限の厳格管理(フォルダロック、ログ管理)
- 退職時に秘密情報返還・廃棄誓約書を取得
- 定期的なコンプライアンス教育
- 内部通報制度の整備
まとめ
- 社員の守秘義務は労働契約から当然に発生し、退職後も続く
- 営業秘密に該当すれば刑事罰+強力な民事措置が可能
- 該当しなくても懲戒解雇・損害賠償は十分可能
- 近年はSNS投稿や私的利用による漏洩も厳しく処罰される傾向
企業側は「秘密管理性を疎かにすると、いざ漏洩しても営業秘密として保護されない」ため、管理体制の構築が最重要です。