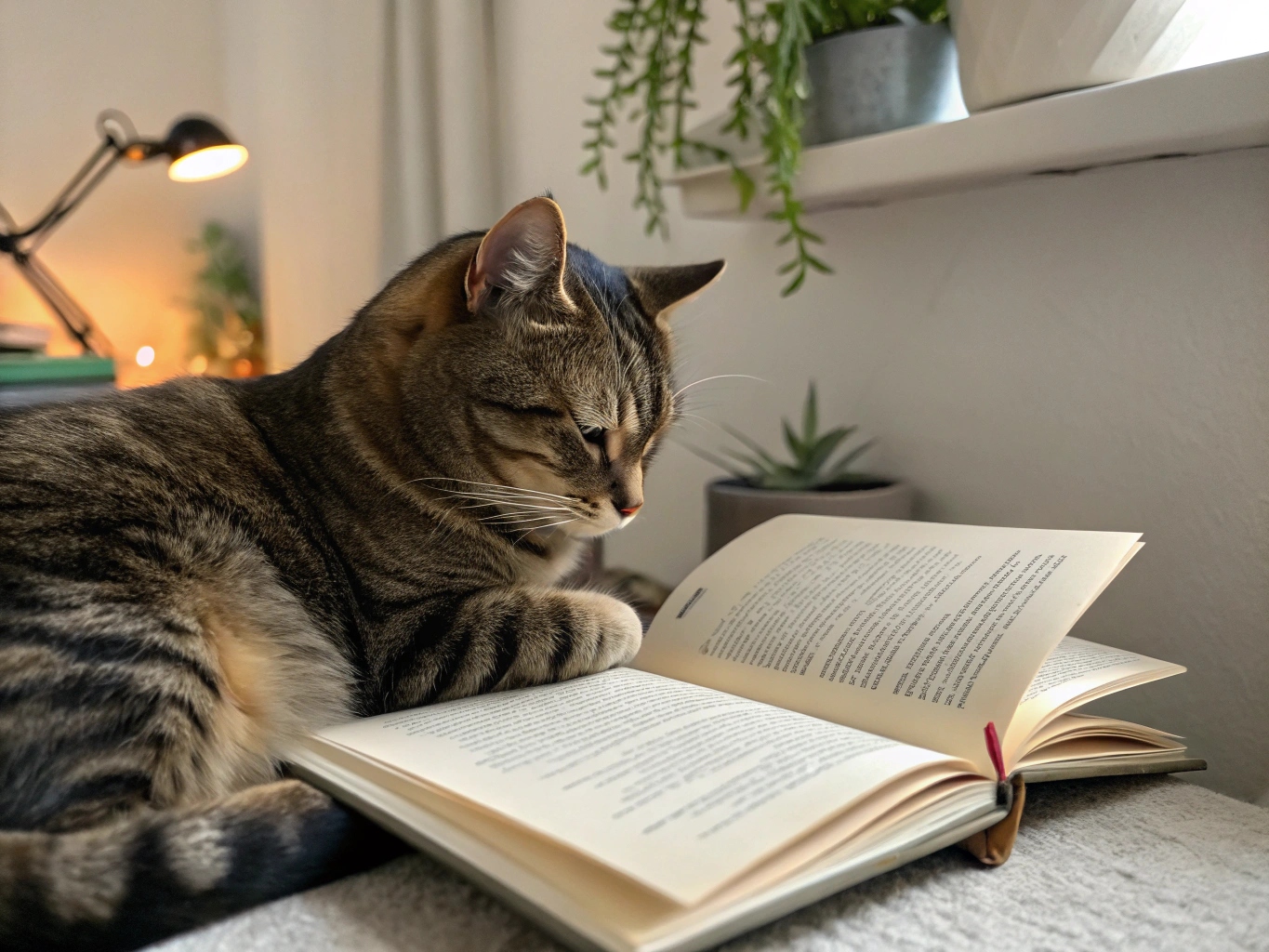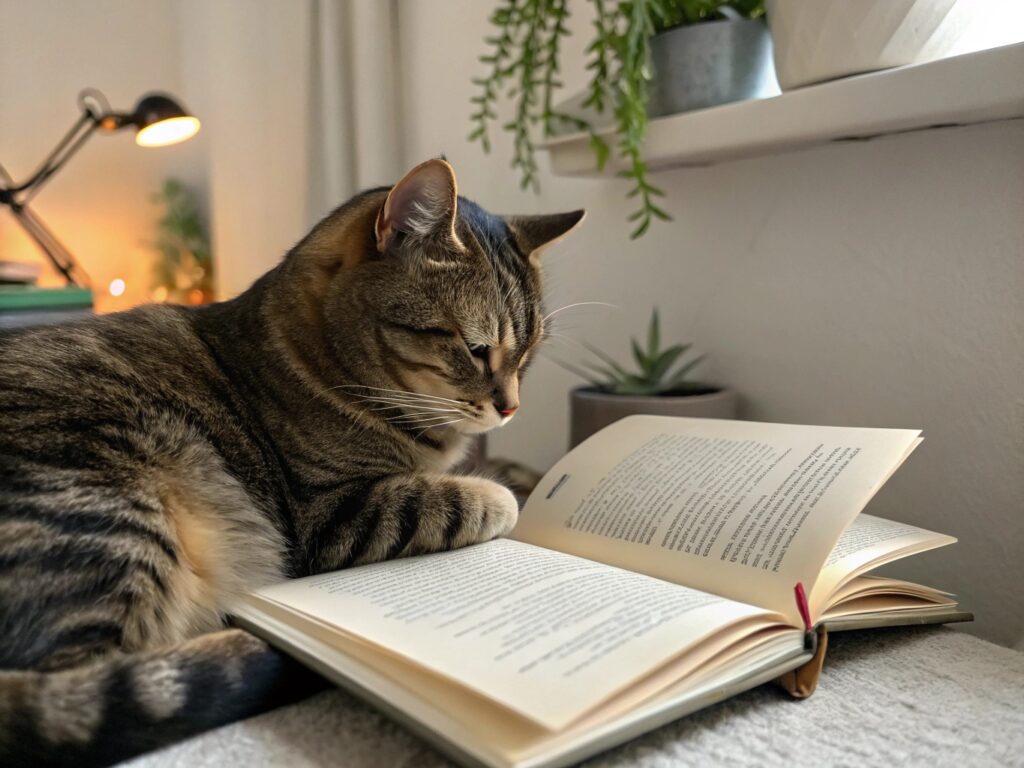
現代乖離説とは、日本の社会学者の宮台真司氏が提唱した社会理論のことです。この理論は、現代社会における個人の生きづらさや社会問題の原因を、**社会の「乖離」**に求めています。
参考文献:『日本の難点』
現代日本の生きづらさはどこから?宮台真司が解き明かす「社会の底抜け」論『日本の難点』要約
乖離とは何か
現代乖離説における「乖離」は、具体的に以下の3つの乖離を指します。
- 意味の乖離
- これは、個人が人生や社会に意味を見出せなくなる状態を指します。昔の共同体では、人々は「家」や「村」といった共通の物語や価値観の中で生き、自分の役割や存在意義を自然と理解していました。しかし、現代社会ではそのような共同体が解体され、誰もが「私」という個人として、自分一人で意味を見つけなければならなくなりました。このため、多くの人が「何のために生きているのか」「自分のしていることに意味があるのか」といった問いに答えを見出せず、生きづらさを感じています。
- 関係の乖離
- これは、人々が「心から信頼し合える深い人間関係」を築くのが難しくなっている状態を指します。現代社会では、家族や職場、地域といった共同体のつながりが薄れ、人間関係が流動的で表面的なものになりがちです。その結果、人は孤独を感じやすく、また、他者との関係性を維持するために「空気を読む」ことや「建前」を使い分けることに疲弊してしまいます。
- 身体の乖離
- これは、個人の「身体」が、社会的な評価や他者からの期待と切り離されてしまう状態を指します。例えば、SNS上での「いいね」やフォロワー数、学歴や年収といった数値化された評価が重視されるようになり、自分の身体を通して感じられる「快・不快」や「生の実感」といったものが軽視される傾向にあります。これにより、自分の感覚を信じられず、他者の評価にばかり振り回されてしまう人が増えています。
現代乖離説が示唆するもの
宮台氏は、これらの乖離が現代の社会問題(例:いじめ、引きこもり、無差別殺傷事件など)の根底にあると考えました。
つまり、現代乖離説は、これらの乖離を克服するためには、単に個人の努力や自己責任に問題を帰するのではなく、**「共通の物語を再構築すること」「深い人間関係を育む場を作ること」「身体的な感覚を大切にすること」**など、社会のあり方そのものを見直す必要がある、というメッセージを投げかけていると言えるでしょう。