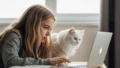日本酒とワインの沈殿物(おり)について
日本酒やワインの「おり(沈殿物)」とは、製造過程で生じた酵母の死骸、タンパク質、色素、澱粉などの粒子が、液体の中で沈殿して底に溜まったものです。これらは酒の風味を形成する一部ですが、混ざると濁りや苦味が増すため、扱いに注意が必要です。日本酒は伝統的に「おり引き」で除去しますが、ワインはデカンタリング(澱引き)が一般的。以下で詳しく説明します!
日本酒のおり
日本酒のおりは、主に酵母の残渣や米由来のタンパク質・澱粉からなります。純米酒や生酒(火入れしていない新鮮酒)に多く、瓶の底に白っぽく沈殿します。
- 原因: 発酵過程で酵母が死に、沈殿。火入れ(加熱殺菌)で溶けやすいものを除去しきれなかった場合に残る。
- 影響: 混ざると酒がにごり、酸味やコクが増します。良い面(にごり酒のまろやかさ)もありますが、クリアな味わいを求めるなら避けたい。
- 例: 獺祭の純米大吟醸や、十四代の生酒でよく見られます。
ワインの沈殿物(リー)
ワインの沈殿物は、主にタンニン(渋み成分)、色素、酵母の残渣で、赤ワインの古酒(ヴィンテージもの)に多いです。白ワインでは稀で、ピンクやオレンジワインで少し見られます。
- 原因: 長期熟成でポリフェノールが凝集したり、酵母が沈殿。ボルドーやブルゴーニュの赤ワインで顕著。
- 影響: 混ざると濁りや渋みが強くなり、香りが鈍る。古酒の魅力(複雑な風味)を守るために除去。
- 例: 1982年ボルドーのシャトー・マルゴーなどの熟成赤ワイン。
日本酒とワインのおりの比較
両者の違いをテーブルでまとめました。共通点は「風味の変化を防ぐために静かに扱う」ことですが、日本酒は米由来で柔らかいおりが多いです。
| 項目 | 日本酒のおり | ワインの沈殿物(リー) |
|---|---|---|
| 主成分 | 酵母死骸、タンパク質、澱粉 | タンニン、色素、酵母残渣 |
| 発生しやすい酒 | 純米酒、生酒、にごり酒 | 赤ワインの古酒(5年以上熟成) |
| 見た目 | 白く柔らかい沈殿(底に溜まりやすい) | 茶色っぽい粒子(壁や底に付着) |
| 混ざった影響 | 濁り、酸味・コクUP(時に苦味) | 渋み増、香り鈍化、濁り |
| 良い面 | 混ぜて飲むとまろやか(にごり酒スタイル) | 複雑な風味の源(デカンタで活かす) |
| 頻度 | 日常的に見られる(特に国産) | 特別な古酒に限る |
扱い方
- 注ぎ方: 両方とも瓶を振らず、ゆっくり傾けて注ぐ。底の1/5は残すか、軽く回して避ける。
- 除去方法:
- 日本酒: おり引き(静置して上澄みだけ飲む)。生酒は冷蔵で沈殿を促す。
- ワイン: デキャンタ(専用の容器に移して澱を残す)。キャンドルライトで底が見えるとプロ級!
- 楽しみ方: おりを意図的に混ぜるのもアリ。日本酒なら「にごり酒」として、ワインなら「オレンジワイン」のように新鮮に味わう。
- 注意: おりが多い酒はラベルに「沈殿あり」と記載。開栓後すぐに飲まず、1-2日置くと沈殿しやすい。