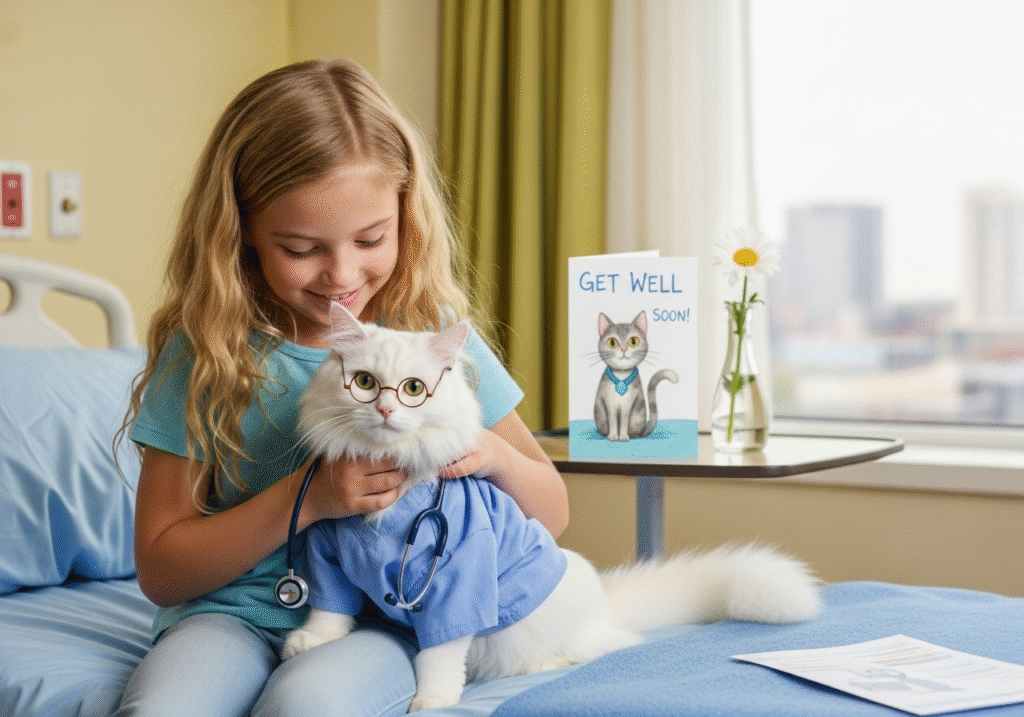
献血はボランティアなので、血液そのものには対価がありません。しかし、原価がゼロではないというのが実態です。献血された血液を、患者さんが安全に輸血できる「輸血用血液製剤」にするまでには、以下のような様々なコストが発生します。
「輸血用血液製剤」にするまでのコスト
1.献血を集めるコスト
献血ルームや献血バスを運営するための人件費、家賃、光熱費、献血に使われる採血針などの消耗品費、広報活動費など、血液を集めるための費用がかかります。
血液事業全体の費用(約1,500億円)のうち、献血推進や採血にかかる費用は約600億円です。
2.安全性を確保するための検査コスト
採血された血液は、輸血によって病気が伝わらないよう、HIV、肝炎ウイルス、HTLV-1など、多くの感染症の有無を厳格に検査します。また、ABO式血液型やRh式血液型などの型判定も行います。これらの検査には、高価な検査機器や試薬、専門の検査技師が必要となります。
輸血用血液製剤の検査費用は、血液事業全体の費用の約15%を占め、約230億円かかっています。
3.血液製剤に加工するコスト
採血された全血を、赤血球、血漿、血小板などの成分ごとに分離し、それぞれの用途に合わせた製剤に加工します。この加工にも、専門の設備や技術が必要となります。
採血した血液を、赤血球製剤、血漿製剤、血小板製剤に分離・加工する費用は、血液事業全体の費用の約20%を占め、約300億円です。
4.供給と管理のコスト
製造された血液製剤は、品質を保つために適切な温度で保管・輸送する必要があります。また、日本全国の医療機関に24時間体制で安定して供給するための物流システムや人件費もかかります。
製造された血液製剤を医療機関に供給・管理する費用は、血液事業全体の費用の約5%を占め、約75億円かかっています。
これらの費用を合計すると、血液製剤1パックあたりの製造・管理コストは数千円~1万円以上になります。日本赤十字社は、これらのコストを賄うために、輸血用血液製剤を医療機関に販売することで、献血事業を維持しています。
このシステムは、「原価がゼロ」の血液をボランティアの善意で集め、それを安全で信頼性の高い医薬品に加工し、必要な患者さんのもとに安定的に届けるための仕組みです。そのため、一見すると「商売」のように見えるかもしれませんが、これは営利を目的としたものではなく、公的な医療サービスを維持するための「事業」と理解するのが適切です。
上記の費用を合計すると、約1,205億円となり、残りの約300億円は研究開発費やその他の事業費に充てられています。
献血が無償提供と有償提供の国について
ボランティアが主流の国
日本をはじめ、多くの国では自発的な無償献血を原則としています。世界保健機関(WHO)は、輸血の安全性を確保する観点から、すべての国が自発的な無償献血を100%達成することを目指しています。79か国が献血の90%以上を自発的な無償献血に依存しており、これは高所得国に多い傾向です。
謝礼や報酬が支払われる国
一方、国や地域によっては、献血に対して金銭的な報酬や謝礼が支払われるケースも存在します。
- アメリカやドイツ: 法律で売血が認められており、献血や特に血漿の提供に対して、数千円相当の金銭や物品が支払われることがあります。
- 韓国: 献血者に証明書が発行され、輸血が必要な際に優先して輸血を受けられる「預血」という制度があります。
- イタリア: 献血のために仕事を休める「献血有給休暇制度」があり、献血を奨励しています。

