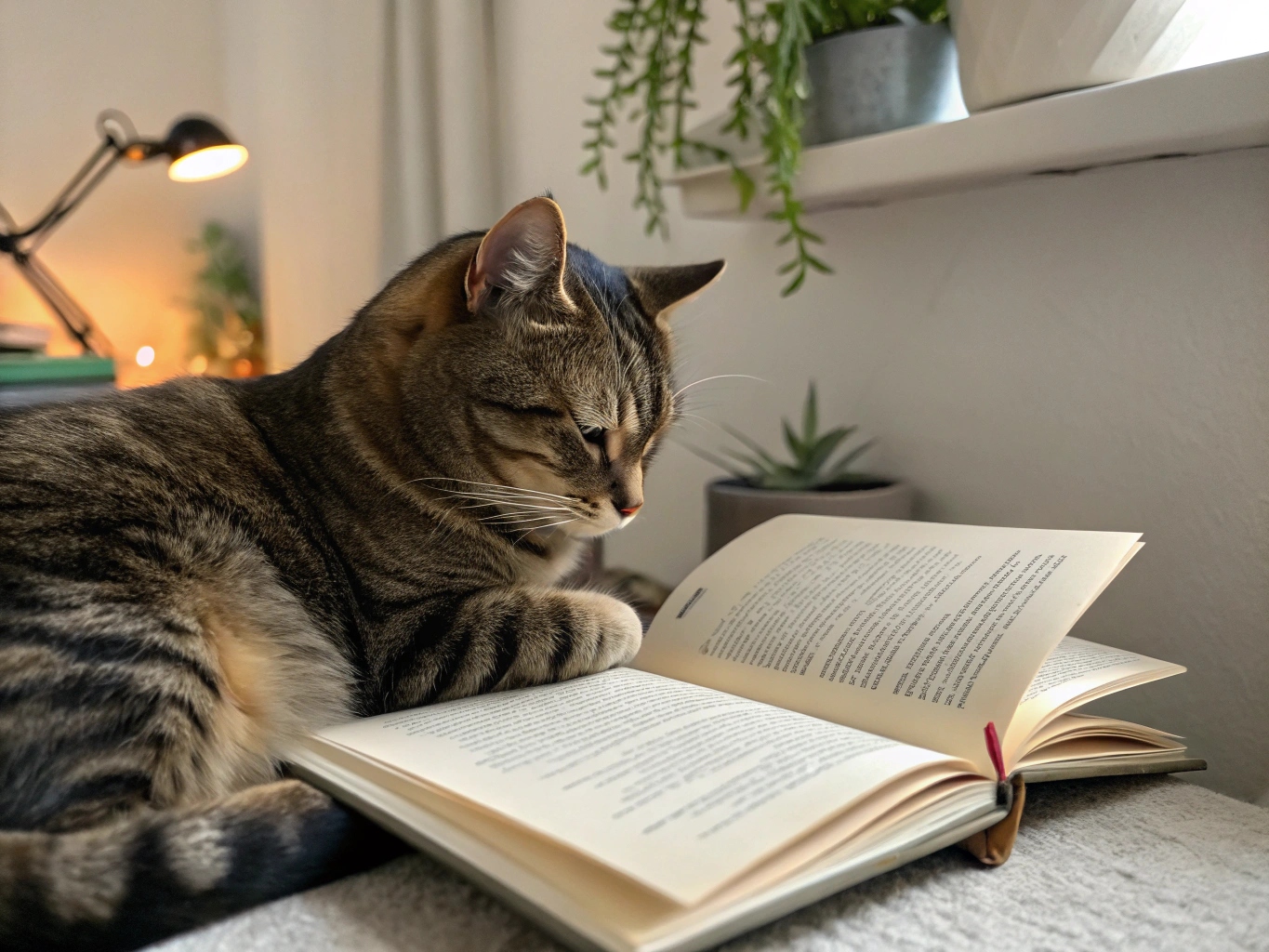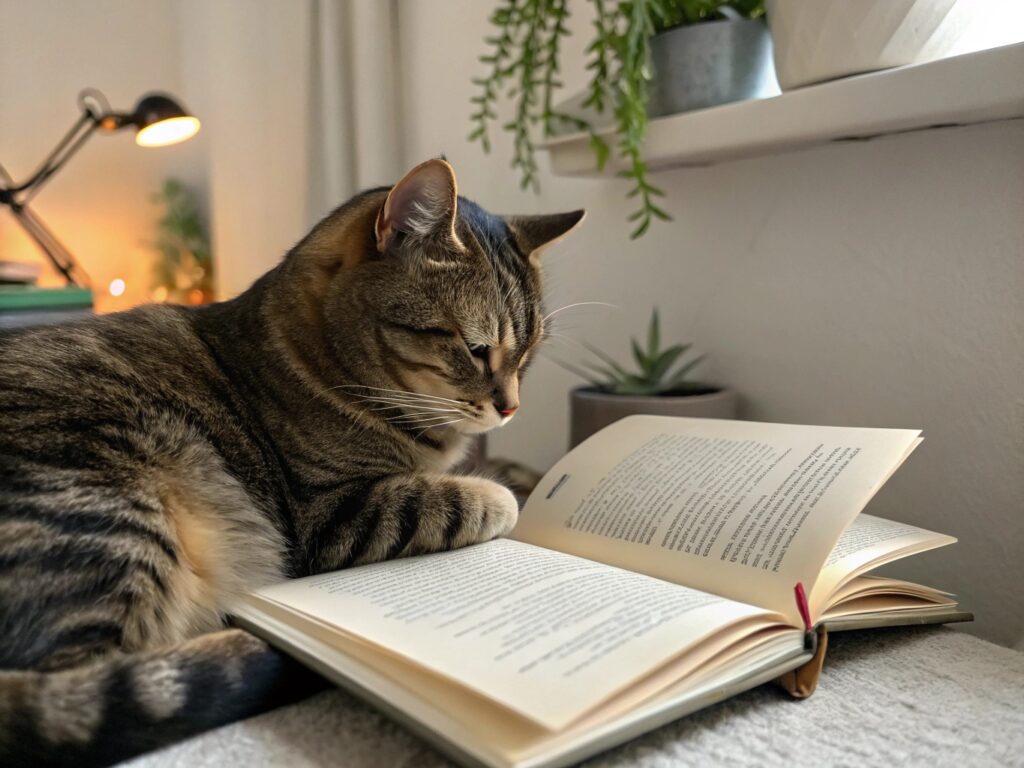
宮台真司の著書『日本の難点』は、現代社会を「社会の底が抜けた時代」と捉え、その原因と処方箋を提示した本です。
参考文献:『日本の難点』
「社会の底抜け」とは
「社会の底抜け」とは、社会学者の宮台真司が提唱した概念で、現代社会が共通の価値観や規範、物語を喪失し、人々のつながりが希薄になった状態を指します。
これは、社会を支える土台や基盤がなくなってしまったような状況で、以下の3つの要素が失われたことで生じるとされます。
- 意味の喪失:誰もが「人生の意味」を共有する物語を持たず、自分一人で意味を探さなければならなくなった状態。
- 関係の喪失:血縁や地縁といった強固な人間関係がなくなり、孤独や希薄なつながりが蔓延した状態。
- 身体の喪失:身体的な感覚や実感よりも、SNSの「いいね」や学歴といった数値化された評価を重視するようになった状態。
宮台氏は、この「社会の底抜け」が、現代社会に蔓延する生きづらさや様々な問題の根本原因であると論じています。
内容の要点
この本は、現代社会を診断するにあたり、以下の3つの段階で議論を展開しています。
- 現状認識:社会の乖離
- 現代の日本社会では、人々が「意味」「関係」「身体」といった、人間らしい生を支える基盤を失い、深い部分で社会と乖離していると指摘します。これが、多くの社会問題(いじめ、無差別殺人など)の根底にあると考えます。
- 背景の分析:ポストモダンと消費社会
- この乖離の背景には、ポストモダンの相対主義や、すべてが商品化される消費社会があると分析します。共通の価値観や物語が失われ、誰もが自分だけの「評価の物差し」を見つけなければならない状況が、生きづらさを生んでいると論じています。
- 処方箋:コミットメントの再構築
- こうした状況を克服するためには、単に個人の努力に頼るのではなく、社会に対して「コミットメント(深い関わり)」を持つことが重要だと説きます。具体的には、自らが主体的に関わることで、社会に意味や関係性を再構築していく必要性を訴えています。
この本は、宮台氏が提唱する「現代乖離説」の考え方を、より具体的に、そして社会全体の問題として掘り下げて解説しているのが特徴です。