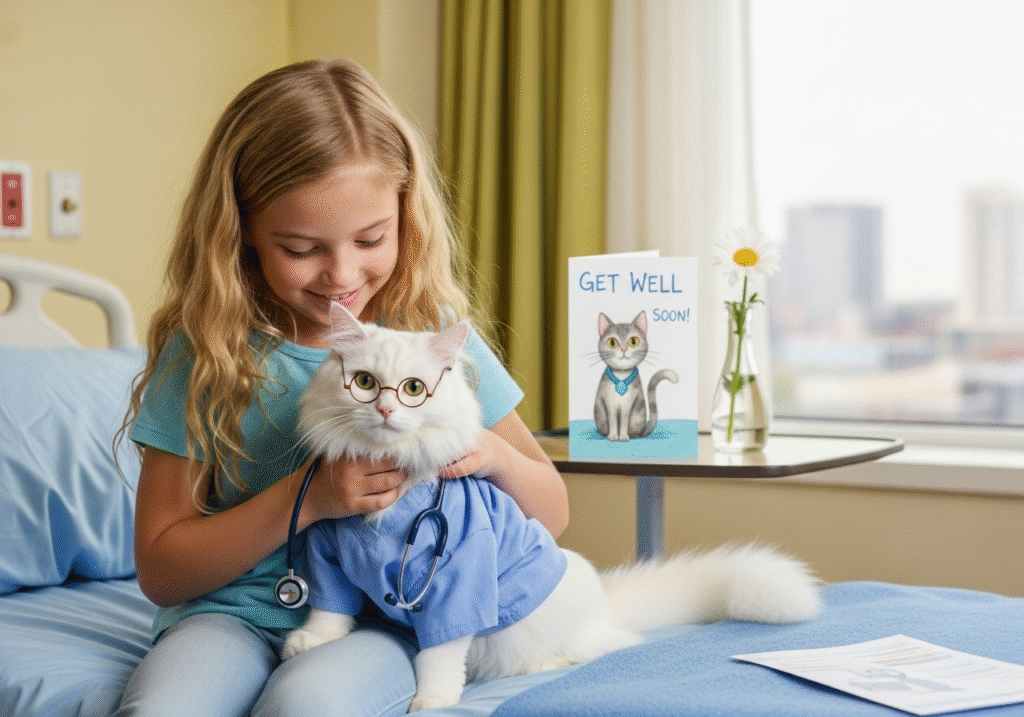
脳出血の治療は、発症からの時間経過と出血部位によって刻々と変化します。特に発症から6時間以内は、出血の拡大を食い止め、脳圧をコントロールする治療が最も予後を左右する「超急性期」です。
脳出血の治療法 段階・場所別に詳しく解説
| 時期 | 目的 | 主な治療内容 | 特に重要なポイント |
|---|---|---|---|
| 超急性期(発症〜6時間) | ①出血の拡大を止める②命を守る | ・血圧管理(収縮期140〜160mmHgくらいに下げる) ・抗凝固薬の中和 ・けいれん予防薬(レベチラセタムなど) | この6時間が一番予後を左右します! 「様子を見よう」は絶対禁物 |
| 急性期(〜72時間) | 脳のむくみ(脳浮腫)を抑える | ・高張液(グリセオール、マンニトール) ・ステロイド(小脳出血の一部) ・頭を30度挙上、過度な酸素は避ける ・体温管理(38℃以上なら解熱) | 脳浮腫のピークは2〜5日目です |
| 手術適応(緊急・準緊急) | 命を取るか、後遺症を減らすか | (下記参照) |
主な手術の種類と適応(2025年現在の標準)
| 出血部位・状態 | 手術名 | 適応の目安 | 手術の目的 | 予後への影響 |
|---|---|---|---|---|
| 小脳出血 | 後頭蓋窩減圧+血腫除去術 | ・血腫径3cm以上 ・意識が悪化傾向 ・第四脳室が圧迫されている | 脳幹圧迫を解除 | 手術すれば生存率が劇的に上がる(6時間以内がベスト) |
| 被殻・視床出血(大量) | 開頭血腫除去術 | ・血腫量30〜50mL以上+意識障害 ・若くて脳ヘルニア兆候あり | 脳圧を下げる | 若い人・右脳なら効果大、高齢者は慎重 |
| 神経内視鏡血腫吸引術(経鼻・経頭蓋) | ・血腫量30mL以上 ・高齢者でも可能 | 低侵襲で血腫を減らす | 最近急速に増えている(入院期間短縮) | |
| 定位脳手術(ステレオ血腫吸引) | ・深部で開頭が難しい場合 | 最小侵襲 | 高齢者・視床出血に多い | |
| 脳室穿破+急性水頭症 | 脳室ドレナージ(外ドレナージ) | ・脳室に大量の血が流入し、意識低下 | 脳圧を下げる | ほぼ全員に行う |
| クモ膜下出血+脳室内血腫 | コイル塞栓術 or クリッピング | 動脈瘤が破れている場合(ほとんど) | 再出血防止 | 発症後72時間以内がベスト |
2025年現在注目されている新しい治療
- 最小侵襲手術(内視鏡+吸引装置)
→ 直径2cm程度の穴で血腫をほぼ100%吸引可能
→ 70歳以上でも安全に施行できるようになった - 中大脳動脈領域の被殻出血に対する減圧開頭術
→ 若い人で大量出血の場合、血腫除去+硬膜を大きく開けて脳の腫れを逃がす
→ 後遺症が明らかに軽くなるデータが蓄積 - 抗凝固薬関連脳出血の中和薬の進化
→ リクシアナ(アピキサバン)、エリキュースに対する即効性中和薬が保険収載
→ 手術までの時間が劇的に短縮
回復期〜慢性期の治療(後遺症対策)
| 後遺症の種類 | 主な治療・リハビリ |
|---|---|
| 片麻痺 | 早期離床、ボツリヌス毒素注射(痙縮に対して)、ロボットリハビリ |
| 失語・高次脳機能障害 | 言語聴覚士による集中的な訓練、経頭蓋磁気刺激(TMS:一部施設) |
| 視床痛(灼けるような激痛) | プレガバリン、ミロガバリン、カルバマゼピン、時にはオピオイド |
| 嚥下障害 | 嚥下造影検査、嚥下リハビリ、胃瘻造設(一時的) |
| てんかん | レベチラセタム、バルプロ酸など(生涯内服が必要な場合も) |
まとめ
- 発症6時間以内が勝負 → すぐに救急車!
- 小脳出血・脳室に血が大量 → ほぼ100%手術が必要
- 若くて大量出血 → 積極的に手術を検討
- 高齢者でも内視鏡手術なら安全にできることが多い
- リハビリは「とにかく早く始める」ほど回復する

