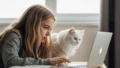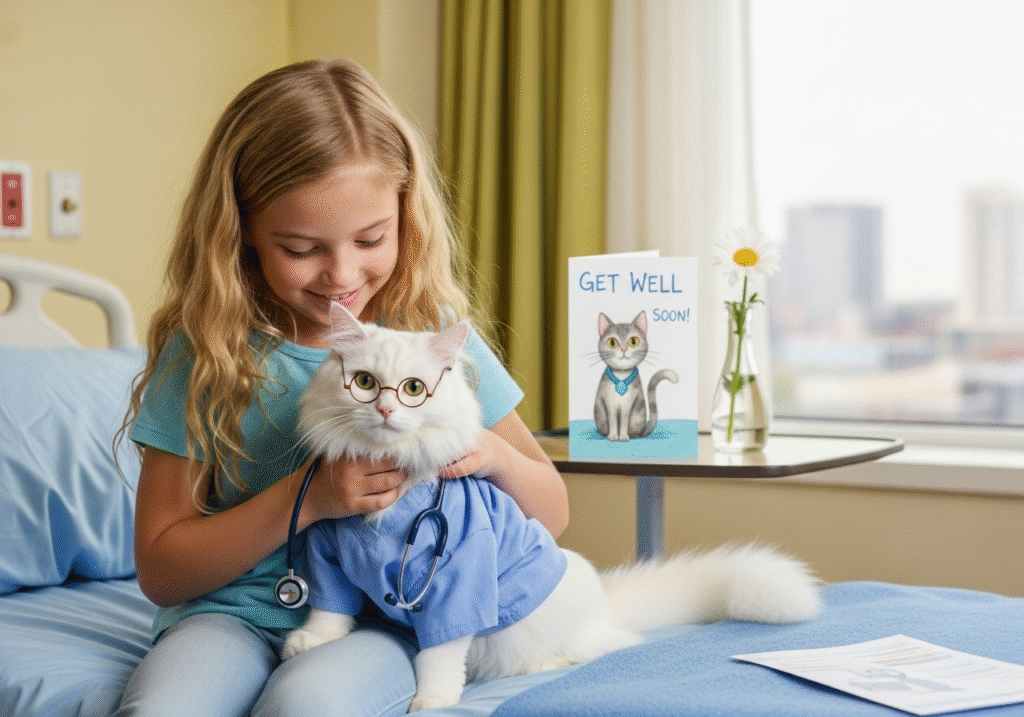
日本の公的医療保険制度には、高額療養費制度があり、1か月(暦月)の医療費負担が一定額を超えた場合に超過分が払い戻される仕組みです。これにより、病気やケガで高額な医療費がかかっても家計への負担を軽減できます。以下に要点をまとめます。
高額療養費制度のポイント
- 目的: 患者さんの医療費負担を軽減すること。
- 対象となる医療費:公的医療保険が適用される診療にかかる自己負担額のみ。
- 対象外の例: 入院時の食費、居住費(差額ベッド代)、先進医療にかかる費用など。
- 計算期間: 毎月1日から末日までの1ヵ月ごとに計算されます。
- 自己負担限度額: 年齢や所得によって異なり、上限額が設定されています。所得が高いほど、自己負担限度額は高くなります。
制度の活用方法
1. 事前に申請する(限度額適用認定証)
- 流れ: 加入している公的医療保険に「限度額適用認定申請書」を提出し、「限度額適用認定証」の交付を受けます。
- メリット: 医療機関の窓口で認定証を提示すれば、窓口での支払いが最初から自己負担限度額までとなります。高額な医療費を一時的に全額立て替える必要がなくなります。
- マイナ保険証を利用できる医療機関では、事前の申請なしで限度額が適用される場合もあります。
2. 事後に申請する(払い戻し)
- 流れ: 医療費を支払った後、加入している公的医療保険に「高額療養費支給申請書」を提出します。
- 特徴: 払い戻しまでには通常、申請から3ヶ月程度かかります。
高額療養費制度の概要
1. 対象者
- 国民健康保険、後期高齢者医療制度、被用者保険(健康保険組合、協会けんぽなど)の加入者全員。
- 生活保護受給者は対象外(医療費全額公費負担のため)。
2. 自己負担上限額(2025年時点の標準額)
上限額は所得区分と年齢で決まります。主な区分は以下の通り。
| 所得区分 | 年収目安 | 70歳未満の上限額(1か月) | 70~74歳の上限額 | 75歳以上の上限額 |
|---|---|---|---|---|
| 上位所得 | 約1,160万円~ | 252,600円 + (総医療費-842,000円)×1% | 252,600円 + (総医療費-842,000円)×1% | 252,600円 + (総医療費-842,000円)×1% |
| 一般 | 約370万円~1,160万円 | 80,100円 + (総医療費-267,000円)×1% | 57,600円 | 57,600円(外来:18,000円) |
| 低所得Ⅱ | 住民税非課税等 | 50,400円 | 24,600円 | 24,600円 |
| 低所得Ⅰ | 住民税非課税かつ所得ゼロ | 35,400円 | 15,000円 | 8,000円 |
※「多数該当」:直近12か月で4回以上高額療養費の支給を受けた場合、4回目以降は上限額が引き下げ(例:一般→44,400円)。
3. 計算の対象となる医療費
- 対象:保険適用内の診療費(入院・外来・薬剤費など)。自己負担分(1割~3割)の合計額。
- 対象外:
- 差額ベッド代、食事代、先進医療費
- 保険外診療(自由診療)
- 入院時の「文書料」など
4. 申請方法
- 自動払い戻し(事前申請不要の場合多し)
- 保険者(市区町村や健康保険組合)が自動計算し、診療月から約3か月後に払い戻し。
- 「限度額適用認定証」の事前取得(おすすめ)
- 入院や高額治療前に保険者へ申請 → 病院窓口で提示すれば支払いが上限額までに。
- 有効期限:通常1年(更新可)。
5. 多数回該当の特例
- 同一世帯で同じ月に複数人が高額療養費対象 → 世帯合算可能。
- 過去12か月で4回目以降の支給 → 上限額がさらに下がる(例:一般は44,400円)。
6. その他の関連制度
| 制度名 | 内容 |
|---|---|
| 付加給付 | 一部の健康保険組合が独自に上乗せ支給(例:上限2万円など) |
| 医療費控除 | 確定申告で年間10万円超の医療費を所得控除 |
| 傷病手当金 | 病気で働けない場合の給与補填(被用者保険) |
まとめ
高額療養費制度は「どんなに医療費がかさんでも、1か月の自己負担は所得に応じた上限まで」というセーフティネットです。
事前に「限度額適用認定証」を取得すれば、窓口での一時負担も軽減されます。