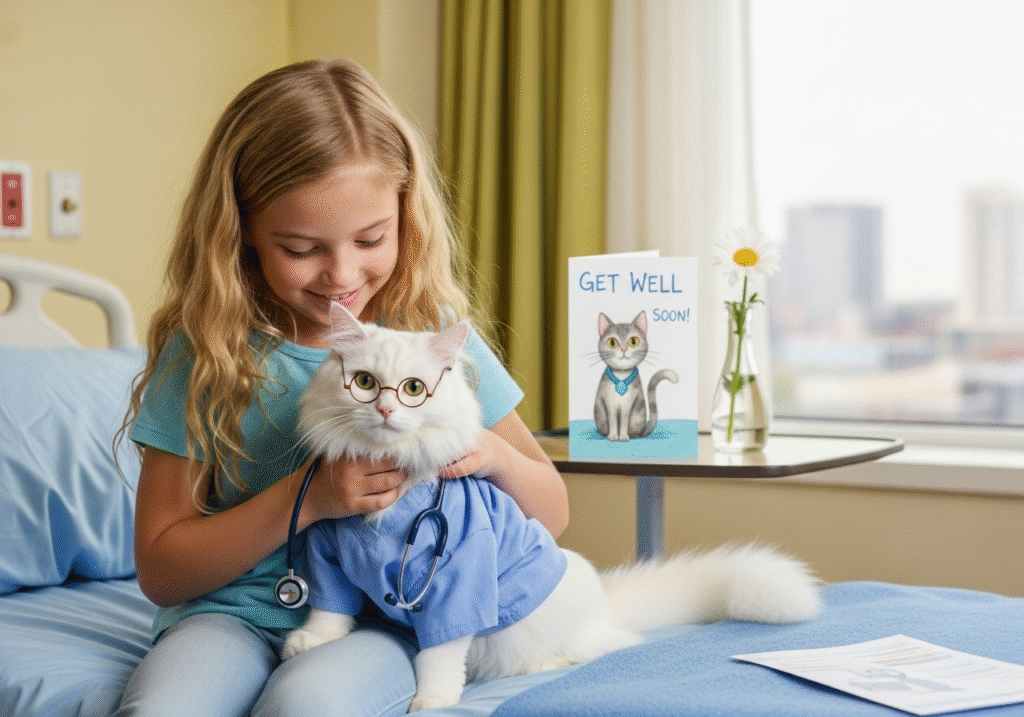
AED(Automated External Defibrillator)は、心臓がけいれんし、全身に血液を送るポンプ機能を失った状態(心室細動)に陥った際に、電気ショックを与えて心臓の動きを正常なリズムに戻すための医療機器です。
2004年7月以降、医療従事者ではない一般市民でも使用が認められ、今では駅や空港、学校、商業施設など、私たちの身近な場所に設置されています。操作は非常に簡単で、音声ガイダンスに従うだけで、誰でも命を救うための重要な役割を担うことができます。
なぜAEDが重要なのか?〜1分が命を分ける〜
人が突然倒れる原因の一つに「心室細動」という致死性の不整脈があります。この状態に陥ると心臓は小刻みに震えるだけで、血液を送り出すことができなくなり、数分で脳に回復不可能なダメージを与え、死に至ります。
この心室細動を止める唯一の効果的な治療法が、電気ショックによる「除細動」です。そして、その効果は時間との勝負です。
総務省消防庁のデータによると、心停止から電気ショックまでの時間が1分遅れるごとに、救命率は約10%ずつ低下するといわれています。救急車の全国平均到着時間は約10分(令和6年版 救急・救助の現況より)であり、救急隊の到着を待っているだけでは手遅れになる可能性が高いのです。
しかし、その場に居合わせた人がすぐに胸骨圧迫(心臓マッサージ)を開始し、AEDを使用することで、救命率は大幅に向上します。何もしなかった場合に比べて、市民がAEDを使用した場合の救命率は約7倍にもなるとの報告もあり、まさに「あなたにしか救えない命」があるのです。
AEDの基本的な使い方(3ステップ)
AEDはフタを開けると自動で電源が入り、その後は音声メッセージが全ての操作を指示してくれます。落ち着いて、ガイダンスに従ってください。
- 電源を入れる(フタを開ける)
- フタを開けると、自動的に電源が入る機種がほとんどです。電源ボタンがある場合は押してください。
- 「落ち着いて、音声ガイドに従ってください」といったメッセージが流れます。
- 電極パッドを貼る
- 倒れている人の衣服を脱がせ、胸をはだけます。
- 電極パッドの袋を破って取り出し、パッドに描かれているイラストの通りに、素肌に直接、しっかりと貼り付けます。(1枚は右胸の上部、もう1枚は左脇腹)
- AEDが「パッドを体に装着してください」と指示してくれます。
- 電気ショックボタンを押す
- パッドが正しく貼られると、AEDが自動的に心電図の解析を始めます。「体に触れないでください」というメッセージが流れたら、自分も周りの人も、倒れている人から離れます。
- AEDが電気ショックが必要と判断すると、「ショックが必要です。充電しています」というメッセージと共に自動で充電が始まり、充電完了後、「ショックボタンを押してください」と点滅で知らせます。
- 周りの人が離れていることを再度確認し、点滅しているショックボタンを押します。
電気ショックの後も、救急隊が到着するまでAEDの指示に従い、胸骨圧迫を続けてください。AEDは必要に応じて、約2分おきに心電図の解析を繰り返します。
使用上の注意点
安全かつ効果的に使用するために、以下の点に注意してください。
- 体が濡れている場合: 汗や水で濡れていると電気が体に伝わりにくくなります。乾いたタオルなどで胸を拭いてからパッドを貼ってください。
- 貼り薬や湿布: 貼ってある場合は剥がし、薬剤を拭き取ってからパッドを貼ります。
- ペースメーカーなど: 胸に硬いこぶのようなもの(植込み型医療機器)がある場合は、その場所を避けてパッドを貼ります。
- アクセサリー類: ネックレスなどの金属類は、パッドに直接触れないように外すか、ずらしてください。
- 女性への使用: 下着はパッドを貼るのに邪魔にならなければそのままで構いませんが、ワイヤー入りブラジャーの場合は、ワイヤーがパッドに触れないように外すか、位置をずらしてください。パッドを貼った後は、上着をかけるなどプライバシーへの配慮をしましょう。
子どもへの使用
- 未就学児(およそ6歳未満): 小児用の電極パッドや、エネルギー量を切り替える「小児用モード」があれば使用します。これらがない場合は、やむを得ず成人用パッドを使用します。その際、2枚のパッドが触れ合わないように、1枚を胸の真ん中、もう1枚を背中の真ん中に貼る方法もあります。
- 小学生以上: 基本的には成人と同じように、成人用パッドを使用します。
AEDはどこにある?〜設置場所の探し方〜
いざという時のために、身の回りのどこにAEDが設置されているかを知っておくことが重要です。
- 日本救急医療財団 全国AEDマップ: スマートフォンアプリやウェブサイトで、現在地周辺や指定した場所のAED設置情報を検索できます。
- 自治体のウェブサイト: 埼玉県などの多くの自治体でも、独自のAEDマップを公開しています。
AEDは、人の命を救うための「勇気のバトン」です。正しい知識を身につけ、もしもの場面に遭遇したら、ためらわずに手を差し伸べてください。

