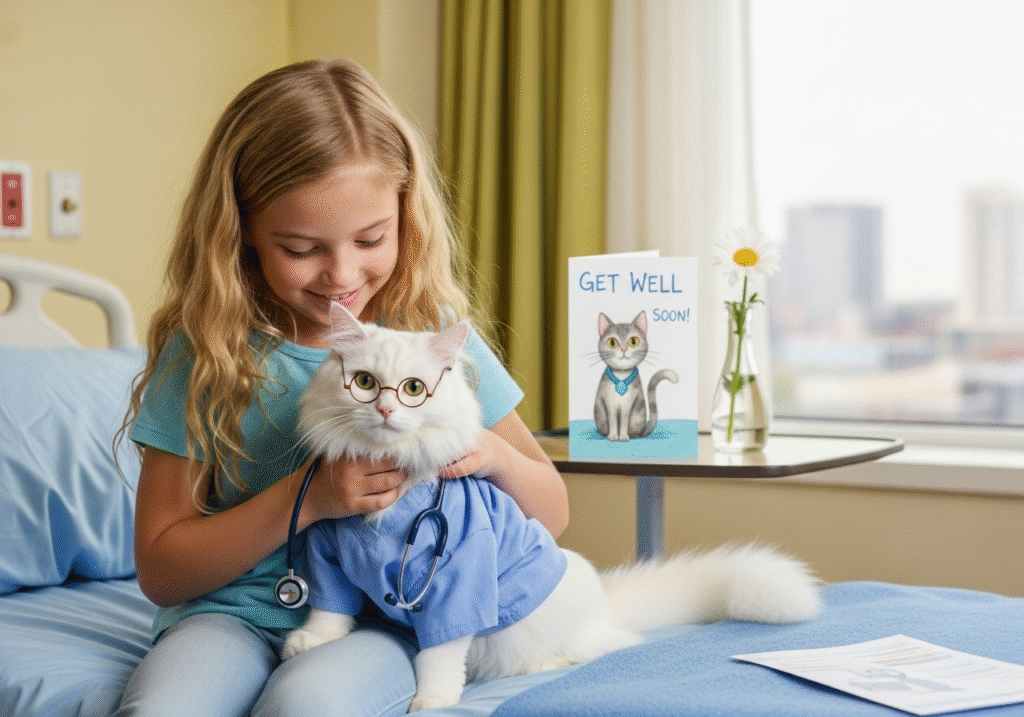
除細動器の臨床応用ガイド(医療従事者向け)
除細動器は、致死性不整脈に対する最も効果的な治療手段の一つであり、その適切な理解と迅速な使用は救命率を大きく左右します。本稿では、マニュアル除細動器を中心に、その機能、適応、臨床使用上の注意点を医療従事者向けに詳述します。
1. 除細動器のモード:非同期と同期
マニュアル除細動器には、主に2つの電気ショックモードがあります。これらは対象となる不整脈と目的によって明確に使い分けられます。
非同期除細動 (Asynchronized Defibrillation)
心電図の波形とは無関係に、任意のタイミングで高エネルギーの電気ショックを与えるモードです。心臓の電気的活動が完全に無秩序な状態を「リセット」することを目的とします。
- 適応:心停止状態にある以下の不整脈
- 心室細動 (Ventricular Fibrillation: VF)
- 無脈性心室頻拍 (Pulseless Ventricular Tachycardia: pVT)
- 特徴: 即時性が求められるため、R波との同期操作は行いません。ACLSアルゴリズムにおける最優先の治療介入です。
同期カルディオバージョン (Synchronized Cardioversion)
心電図のR波を機器が認識し、それに同期して(タイミングを合わせて)電気ショックを与えるモードです。心室の絶対不応期(T波の頂点付近)への通電を避けることで、より致死的なVFへの移行(R-on-T)を防ぎます。
- 適応: 脈拍はあるが血行動態が不安定な頻脈性不整脈
- 心房細動 (Atrial Fibrillation: Afib) / 心房粗動 (Atrial Flutter: AFL)
- 発作性上室性頻拍 (Paroxysmal Supraventricular Tachycardia: PSVT)
- 単形性心室頻拍 (Monomorphic VT)
- 操作上の注意:
- 必ず**「SYNC」ボタン**を押し、モニター上でR波を正しくセンシングしているか(マーカーが表示されるか)を確認します。
- ショックボタンは押し続ける必要があります。機器がR波を検知した瞬間に通電するため、ボタンを押してから実際に通電するまでわずかなタイムラグが生じます。
- 1回のショックごとに同期モードは解除される機種が多いため、連続して行う場合は再度「SYNC」ボタンを押す必要があります。
2. エネルギー設定:二相性と単相性
二相性(Biphasic)除細動器の場合
現在、臨床現場のほとんどがこのタイプです。
- 基本的な推奨: 初回のエネルギーは、各除細動器メーカーが推奨する値(通常 120〜200J)を使用します。
- メーカー推奨値が不明な場合: 最大エネルギーを選択します。
- 実臨床での考え方: 除細動の成功率を最大限に高め、心停止時間を短縮するため、初回から最大エネルギー(200Jなど)を選択することを是とする考え方が広まっています。低エネルギーで失敗し、再度充電・ショックを行う時間的ロスを防ぐメリットが重視されています。
- 2回目以降: 1回目で除細動が成功しなかった場合は、前回と同等か、より高いエネルギー(最大値まで)を使用します。
ポイント 💡 二相性除細動器は、単相性に比べて少ないエネルギーで心筋へのダメージを抑えつつ高い除細動効果が得られます。そのため、「最大」と言っても、かつての単相性360Jのようなダメージを常に懸念するわけではなく、むしろ初回での確実な除細動を優先する傾向にあります。
単相性(Monophasic)除細動器の場合
旧式のタイプで、現在はあまり使用されません。
- 推奨: 初回から360Jを使用します。
なぜ「最大から」という考え方が主流なのか?
主な理由は**「除細動の成功率」と「時間短縮」**にあります。
- 初回成功率の向上: 低いエネルギーでショックを行って失敗した場合、再度胸骨圧迫を中断し、充電し、ショックを行う必要があります。この中断時間は救命率に悪影響を与えます。初回から成功率の高い高エネルギーを用いることで、この中断を最小限にできる可能性があります。
- 高エネルギーの安全性: 二相性除細動器における高エネルギー(例: 200J)が、低エネルギーに比べて心筋障害などの有害事象を著しく増加させるという明確なエビデンスは限定的です。そのため、除細動が成功するメリットの方が大きいと判断されています。
ACLSガイドラインでは、二相性除細動器の使用が推奨されています。
3. 多機能除細動器の活用
現代の除細動器は、電気ショック機能に加え、診断と治療をサポートする多様な機能を搭載しています。
経皮的ペーシング (Transcutaneous Pacing: TCP)
体表に貼付したパッドを介して心臓に電気刺激を与え、心拍を確保する機能です。
- 適応: 薬物療法に反応しない症候性の徐脈(完全房室ブロック、Mobitz II型房室ブロック、洞機能不全など)で、血行動態が不安定な場合。恒久的ペースメーカー植込みまでのブリッジ治療として用いられます。
- 手順:
- 鎮静・鎮痛を考慮します(意識のある患者には苦痛を伴うため)。
- ペーシングモードを選択し、レート(通常60〜80回/分)を設定します。
- 徐々に電流(mA)を上げていき、心電図上でペーシングスパイクに続いてQRS波が確実に出現する(ペーシングキャプチャー)最小の電流値(閾値)を確認します。
- 大腿動脈などで脈拍を触知し、実際に心拍出が得られているか(メカニカルキャプチャー)を確認します。
- 設定電流は、閾値よりわずかに高く設定して維持します。
モニタリング機能
- 12誘導心電図: ACS(急性冠症候群)の迅速な診断に不可欠です。
- SpO₂(経皮的動脈血酸素飽和度): 呼吸状態の評価に用います。
- EtCO₂(呼気終末二酸化炭素分圧): CPRの質の評価(35〜45mmHgが目標)、自己心拍再開(ROSC)の早期検知(EtCO₂の急激な上昇)、気管チューブの適切な位置確認に極めて有用です。
- NIBP(非観血的血圧測定)
4. その他の除細動器
植込み型除細動器 (Implantable Cardioverter Defibrillator: ICD)
心室細動や心室頻拍による心臓突然死のハイリスク患者の体内に植え込むデバイス。致死性不整脈を自動で検知し、抗頻拍ペーシングや電気ショックを作動させます。

