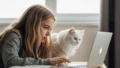定額減税(1人4万円)で税金を引ききれなかった方必見!この記事では、減税しきれない額を補填する「調整給付金」の仕組みと、2025年に支給される「不足額給付(追加給付)」の対象者を具体例を交えて詳しく解説します。所得減少や扶養家族の増加で給付金が増えるケース、事業専従者への定額支給など、あなたがもらえる金額と手続きがすべてわかります。
1. 定額減税の基本
| 項目 | 内容 |
| 目的 | 物価高騰による国民の負担を軽減し、手取り収入を増やすための国の経済対策。 |
| 減税額 | 1人あたり合計4万円(所得税3万円+住民税1万円)。 |
| 対象者 | 納税者本人と、扶養している配偶者・扶養親族(所得制限あり)。 |
| 実施時期 | 2024年6月から。給与や賞与、住民税の納付額から順次減税される。 |
2. 調整給付金(定額減税補足給付金)
定額減税の総額(4万円 × 人数)が、実際に納める税金の額よりも多く、**「税金を引ききれない(減税しきれない)」**方に対して、その不足分を補うために自治体から支給される給付金です。
(1) 当初調整給付(2024年夏頃に支給)
| 項目 | 内容 |
| 対象 | 2024年夏頃の推計で、定額減税しきれないと見込まれた方。 |
| 支給額 | 「減税しきれない額の合計」を1万円単位で切り上げて支給。 |
| 計算方法 | (定額減税可能額 – 推計税額) を算出し、1万円単位に切り上げる。 |
| 例 | 減税しきれない額が14,500円の場合、切り上げで20,000円が支給される。 |
(2) 不足額給付(追加支給・不足額給付Ⅰ)(2025年以降に支給)
当初調整給付を受けたものの、その後に「令和6年分の所得税額」が確定した結果、当初の給付額では不足が生じた方への追加給付です。
| 不足額が生じる主な具体例 |
| ① 令和6年中の所得が当初の推計より減少した(例:年の途中で退職・事業不振) |
| ② 令和6年中に扶養親族が増加した(例:子どもの出生) |
| ③ 税額の更正・修正申告があった |
(3) 不足額給付(定額支給・不足額給付Ⅱ)(2025年以降に支給)
定額減税も、低所得者向け給付金も、どちらの恩恵も受けられなかった方に対する救済措置です。
| 不足額給付Ⅱの主な具体例 | 支給額(原則) |
| **① 課税世帯の事業専従者(青色・白色)**で、自身の税額が非課税レベルの方 | 4万円(定額) |
| ② 課税世帯の合計所得金額が48万円超で、自身の税額が非課税レベルの方 | 4万円(定額) |
| ③ 令和6年1月1日時点で国外居住だった方(所得税分のみ対象) | 3万円(定額) |
支給金の計算方法と具体例
当初に支給される**調整給付金(定額減税補足給付金)**の額は、一律の定額ではなく、世帯の定額減税可能額(4万円 × 人数)が、実際に納める税額をどれだけ上回るかによって決まります。
算出された不足額を1万円単位で切り上げて支給されます。
当初調整給付額の計算方法
当初の調整給付は、2024年(令和6年)度の税額がまだ確定していないため、前年(令和5年)の課税情報などを用いて推計で計算されました。
- 所得税分の控除不足額を計算する所得税分の控除不足額=定額減税可能額(3万円×人数)−令和6年分推計所得税額(減税前)(※ マイナスになる場合は0円とする)
- 住民税分の控除不足額を計算する住民税分の控除不足額=定額減税可能額(1万円×人数)−令和6年度個人住民税所得割額(減税前)(※ マイナスになる場合は0円とする)
- 合計額を1万円単位で切り上げる調整給付額=(所得税分の控除不足額+住民税分の控除不足額)を1万円単位で切り上げた額
具体的な計算例
| 世帯構成 | 定額減税可能額 (A) | 減税前の税額の合計 (B) | 減税しきれない額 (A) – (B) | 調整給付額 (1万円単位で切り上げ) |
| 単身者 (4万円可能) | 40,000円 | 25,500円 | 14,500円 | 20,000円 |
| 夫婦 (8万円可能) | 80,000円 | 71,900円 | 8,100円 | 10,000円 |
| 3人家族 (12万円可能) | 120,000円 | 110,000円 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3人家族 (12万円可能) | 120,000円 | 100,000円 | 20,000円 | 20,000円 |
| 単身者 (4万円可能) | 40,000円 | 39,900円 | 100円 | 10,000円 |
このように、実際に減税しきれない額が100円であっても、1万円に切り上げられて10,000円が支給されます。
もし、この当初の調整給付額でも足りなかった場合(例:年の途中で所得が大きく減ったなど)は、後から**「不足額給付」**として追加で支給されます。