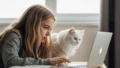「NISAとiDeCo、どっちを始めるべき?」という疑問を解決! 2025年最新の制度に基づき、両者の目的(柔軟な資産形成 vs 老後資金)、節税効果(運用益非課税 vs 所得控除)、60歳までの引き出し制限といった決定的な違いを分かりやすい比較表で徹底解説。初心者におすすめの制度と、理想的な「併用術」をご紹介します。
NISAとは? iDeCoとは?
まず、簡単に概要を説明します。
NISA(少額投資非課税制度)
株式や投資信託などの金融商品の運用益(売却益や配当金)が非課税になる制度です。2024年から「新NISA」としてリニューアルされ、非課税期間が無期限化され、投資枠が拡大(つみたて投資枠:年120万円、成長投資枠:年240万円、生涯投資上限1,800万円)。中長期的な資産形成に適しており、いつでも売却・引き出しが可能。18歳以上なら誰でも利用できます。
【初心者向け】NISAとは? 初心者向けに超わかりやすく解説!
iDeCo(個人型確定拠出年金)
自分で老後資金を積み立てる私的年金制度。掛金が全額所得控除(所得税・住民税の節税)され、運用益も非課税。受け取り時(60歳以降)も退職所得控除や公的年金等控除が適用。加入は20歳以上60歳未満で、加入者の種類(会社員、自営業など)により掛金上限が異なり(月5,000円〜68,000円)、原則60歳まで引き出し不可。
両者は「運用益非課税」という共通点がありますが、目的(NISA:家計全体の資産形成、iDeCo:老後年金)が異なり、併用が可能です。2025年現在、両制度とも人気で、初心者には新NISAの柔軟さがおすすめされることが多いです。
NISAとiDeCoの違いの比較
以下に、主な違いをテーブルでまとめます。2025年時点の制度に基づいています。
| 項目 | NISA(新NISA) | iDeCo |
|---|---|---|
| 目的 | 中長期的な資産形成(教育資金、住宅資金など)。柔軟な運用が可能。 | 老後資金の準備(年金として)。長期運用前提。 |
| 対象者 | 18歳以上(60歳以上も可)。誰でも加入可能。 | 20歳以上60歳未満。企業型DC加入者も一部加入可。 |
| 掛金(投資額) | つみたて投資枠:年120万円 成長投資枠:年240万円 生涯上限1,800万円 | 月5,000円〜(上限は加入者区分による:会社員27,500円〜、自営業68,000円)。生涯上限なし。 |
| 非課税内容 | 運用益(売却益・配当金)非課税。拠出時・受取時は課税。 | 拠出時:全額所得控除(節税)。 運用益:非課税。 受取時:退職所得控除 or 公的年金等控除。 |
| 非課税期間 | 無期限(売却後も再投資可能)。 | 運用中無期限。受取は60歳以降。 |
| 引き出し | いつでも自由(売却可能)。損益通算不可。 | 原則60歳まで不可(例外:死亡時など)。継続積立必須(休止可)。 |
| 対象商品 | つみたて枠:低コスト投資信託のみ。 成長枠:株式、ETF、投資信託など幅広い。 | 投資信託、定期預金、保険商品(元本確保型含む)。商品数はNISAより少ない。 |
| 手数料 | 口座開設・維持無料(運用商品による)。 | 口座管理手数料(月数百円)+運用手数料。 |
| メリット | ・柔軟性が高い(いつでも現金化)。 ・商品選択肢が多い。 ・一括投資可。 | ・節税効果が大きい(高所得者ほどお得)。 ・老後資金に特化。 |
| デメリット | ・拠出時の節税なし。 ・元本割れリスク(投資商品のみ)。 | ・流動性低い(60歳までロック)。 ・商品選択肢が限定的。 |
| 向いている人 | ・短期〜中期資金が必要。 ・積極投資したい人。 ・初心者で少額から始めたい人。 | ・高所得者(節税重視)。 ・老後資金を確実に積み立てたい人。 |
どちらを選ぶ?併用のすすめ
- NISAをおすすめする場合:資金の自由度を重視する人。2025年現在、非課税枠の拡大で人気で、つみたて投資枠は低リスクの積立にぴったり。投資初心者や、住宅・教育資金を準備したい人に最適。
- iDeCoをおすすめする場合:年収が高い人(例:年収500万円以上で掛金2.3万円の場合、年間約5万円の節税可能)。老後資金を強制的に貯めたい人に。
- 併用をおすすめ:両方利用可能で、iDeCoで老後資金を固め、NISAで残りの資金を運用するのが理想。総投資額を最大化でき、節税+柔軟性を両立。
詳細は金融庁の公式サイトや金融機関で確認を。投資は元本保証がないので、リスクを理解して始めましょう。