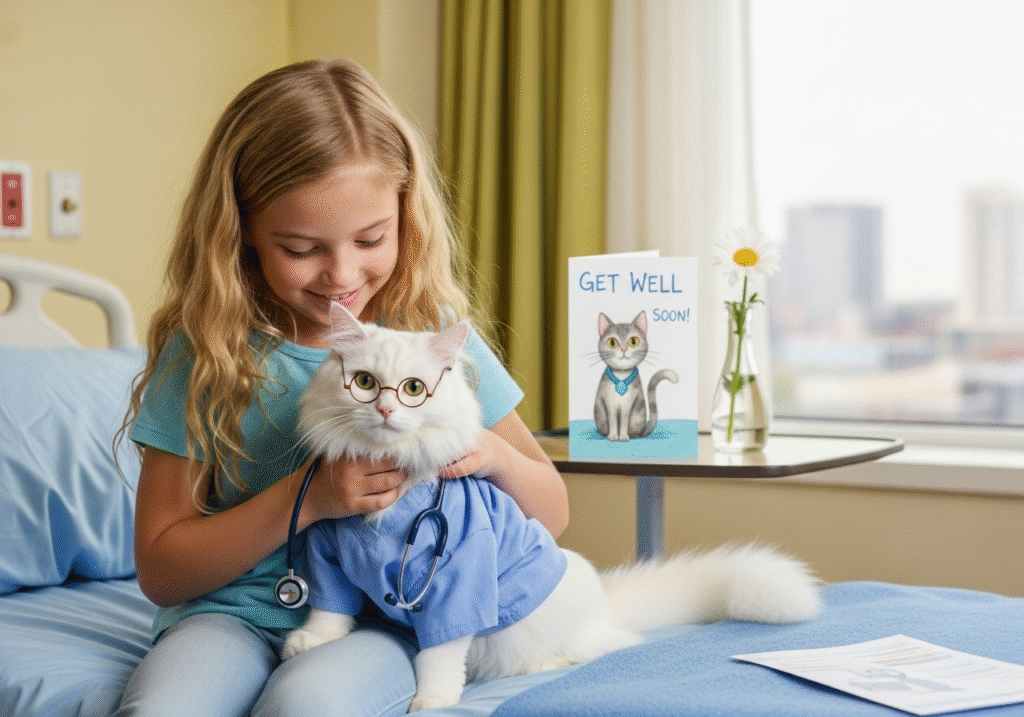
尿路結石の治療法は、結石の大きさ・位置・症状の重さによって異なります。基本的に保存的治療(自然排出を促す)から外科的治療まで選択されます。以下で詳しく説明します。情報は日本泌尿器科学会ガイドラインや各医療機関のデータに基づき、2024-2025年時点の一般的な目安です。個別のケースでは医師の判断が優先されます。
1. 治療法の概要
治療の選択肢を表にまとめました。主な方法は以下の通りで、すべて健康保険適用です。
| 治療法 | 適応例 | 詳細 | 入院の有無・期間の目安 |
|---|---|---|---|
| 保存的治療(自然排出促進) | 結石5mm以下、無症状または軽症 | 水分摂取(1日2-3L以上)、痛み止め(NSAIDs)、αブロッカー(尿管拡張薬)。約80%が自然排出。 | 入院不要(外来)。重症時は1-2日観察入院。 |
| 体外衝撃波砕石術 (ESWL) | 1cm以下の腎・尿管結石 | 体外から衝撃波で結石を粉砕。痛み少なく、日帰り可能。複数回必要の場合あり。 | 入院不要または2-3日(痛み管理や合併症観察)。 |
| 経尿道的尿管砕石術 (TUL/f-TUL) | 尿管・腎結石(2cm以下)、中下部尿管結石 | 尿道から内視鏡を挿入し、レーザー(ホルミウムYAG)で砕石・摘出。軟性鏡使用で腎結石も対応。 | 入院3-5日(ステント留置の場合、追加1-2週間外来フォロー)。 |
| 経皮的腎砕石術 (PNL) | 2cm以上の大結石、サンゴ状結石 | 背中から1cm程度の穴を開け、内視鏡で直接砕石・摘出。出血リスクあり。 | 入院5-10日(合併症観察)。 |
| 組み合わせ治療 (ECIRS: TUL+PNL) | 非常に大結石(3cm以上) | TULとPNLを同時/連続施行。効率化で回数削減。 | 入院7-10日。 |
| 開腹/腹腔鏡手術 | 稀(ESWL/TUL不適応の複雑例) | 従来法で侵襲大。近年減少。 | 入院7-14日。 |
- 緊急時対応: 感染合併(発熱・敗血症疑い)時は、まず尿管ステントや経皮腎瘻(ネフロストミー)で尿路確保。抗生剤併用。
- 成功率: ESWL 70-90%、TUL 90%以上。合併症(出血・感染)は5-10%程度。
2. 入院期間の目安
入院は治療法や患者の状態(年齢、合併症)で変動します。近年、内視鏡治療の進歩で短縮傾向(平均3-7日)。高齢者(65歳以上)や感染合併時は長引く可能性あり。
- 全体平均: 尿路感染合併例で12日(全国データより)。
- 要因: 結石サイズ大、複数回治療、ステント留置時(退院後1-2週間で抜管)。
- 日帰り可能: 小結石のESWLや軽症TULで対応可。仕事復帰は入院前後+1-2日休養推奨。
3. 診療報酬(医療費・保険適用)
日本では健康保険(国民健康保険/協会けんぽなど)が適用され、3割負担が標準(高齢者・低所得者は1-2割)。診療報酬は点数制(1点=10円)で、DPC(診断群分類)制度により入院基本料が定額化。2024年度改定で内視鏡治療の効率化が推進され、点数が微調整(例: TUL関連の施設基準強化)。
- 費用目安(3割負担、税込):治療法総医療費目安患者負担目安備考保存的治療1-5万円数千円-1.5万円外来中心。検査費含む。
- ESWL10-20万円3-9万円1回分。複数回で追加。
- TUL20-40万円6-12万円入院3-5日分含む。ステント追加1-2万円。
- PNL30-50万円9-15万円入院5-10日分。出血管理で変動。
- 全体入院(感染合併)50-100万円15-30万円12日平均で約42万円総額(1USD≈150円換算)。
- 内訳: 入院基本料(1日2-3千点=2-3万円)、手術料(ESWL: 約1,000点、TUL: 約2,000-3,000点)、検査・薬剤。DPC適用病院で定額化され、短期間治療でコスト抑制。
- 追加支援: 医療費助成(高額療養費制度)で月負担上限(例: 一般所得8-10万円)。生命保険の入院給付金適用可(手術分類)。
- 2024年度改定ポイント: 泌尿器科専門医配置の施設で加算(例: TUL点数+50点)。詳細は厚生労働省サイトで確認を。
注意点
- 費用変動要因: 病院規模、合併症、地域差(都市部高め)。事前見積もり(任意継続診療報酬請求書)推奨。
- 予防再発: 治療後、成分分析と生活指導で再発率50%を抑制。
- 症状悪化時は即泌尿器科受診。個別相談は主治医へ。

