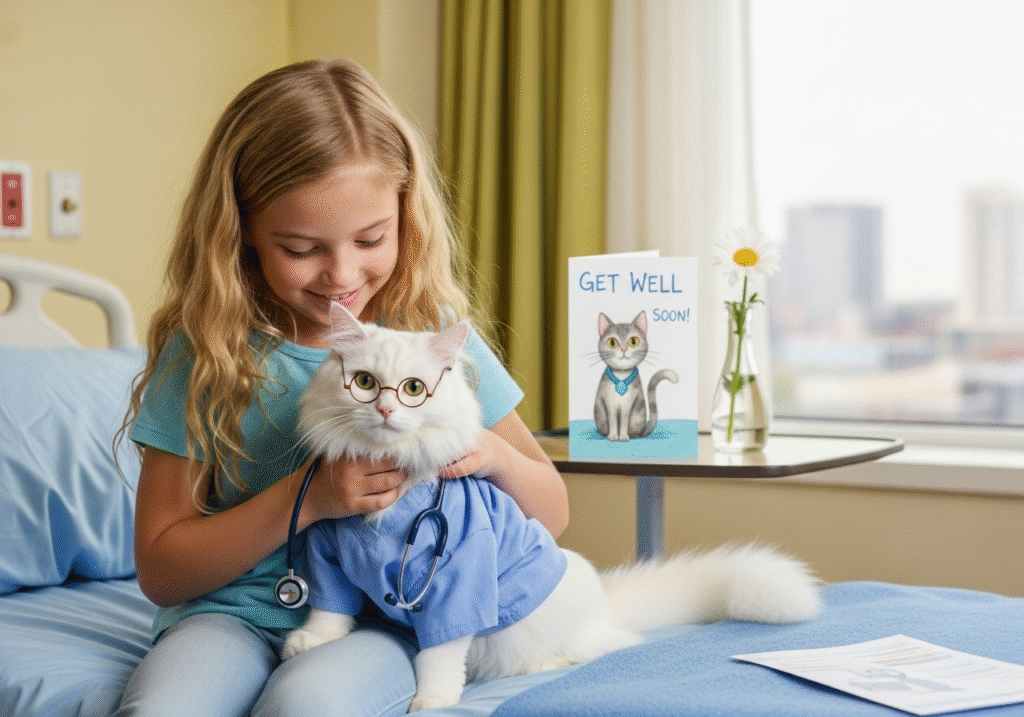
2025年現在の医療ガイドライン(日本消化器病学会の胃潰瘍診療ガイドラインなど)に基づき、信頼できる医療機関の情報源から抽出しています。治療は個人の症状や原因により異なりますので、必ず医師に相談してください。
1. 治療法
胃潰瘍の治療は、主に薬物療法が中心で、ピロリ菌除菌を組み合わせることで治癒率90%以上が期待できます。手術は合併症時のみです。治療期間は通常6〜8週間で、内視鏡で治癒を確認します。
- 薬物療法(主なもの):
- 胃酸分泌抑制薬:
- プロトンポンプ阻害薬(PPI): オメプラゾール(オメプラール)、ランソプラゾール(タケプロン)など。胃酸を強力に抑え、潰瘍の治癒を促進。1日1回服用、8週間程度。
- カリウムイオン競合型酸ブロッカー(P-CAB): ボノプラザン(タケキャブ)。PPIより速効性が高く、重症例に適する。
- H2ブロッカー: ファモチジン(ガスター)など。軽症時に使用。
- ピロリ菌除菌療法: 感染が確認された場合、PPI+アモキシシリン+クラリスロマイシンの3剤併用で1週間。成功率は初回90%以上、再除菌でさらに向上。除菌成功で再発リスクが大幅低下。
- 胃粘膜保護薬: スルファテテーブル(ムコスタ)、レバミピド(ムコゲン)など。潰瘍の修復を助け、NSAIDs使用時の予防にも。
- その他: 出血時は輸血や鉄剤で貧血治療。絶食+点滴で胃を休める場合あり。
- 胃酸分泌抑制薬:
- 生活療法: 禁煙・節酒、刺激物(辛い食べ物、コーヒー)避け、少量頻回の食事。ストレス管理(散歩など)。
- 内視鏡治療: 出血時は内視鏡で止血(クリップ止血や電気凝固)。穿孔時は外科手術(胃切除や縫合)。
- 手術: まれ(全体の1%未満)。穿孔・大量出血・狭窄時。腹腔鏡手術が増え、回復が早い。
治療の流れ: 診断(内視鏡)→原因特定(ピロリ検査)→薬開始→4週間後内視鏡再検査→8週間で最終確認。
2. 入院期間
入院の必要性は症状の重さで決まります。軽症(無症状や軽い痛み)は外来通院で完治可能ですが、重症例では観察が必要です。2025年現在、DPC(診断群分類)制度で効率化が進み、短期入院が増えています。
| 症状の重さ | 入院の目安 | 期間の例 | 理由 |
|---|---|---|---|
| 軽症(痛みのみ) | 不要(外来) | – | 薬で管理可能。定期通院で経過観察。 |
| 中等症(貧血・出血少量) | 入院推奨 | 3〜7日 | 点滴・止血処置。症状安定後退院。 |
| 重症(大量出血・穿孔) | 必須 | 1〜2週間(合併症で長期化) | 絶食・輸血・手術。穿孔時は2週間以上。 |
- 平均入院日数: 約7〜10日(DPCデータより)。2025年の地域医療構想で、在宅移行を促進し短期化傾向。
- 注意: 高齢者や基礎疾患ありは長引く可能性。緊急時は救急入院。
3. 診療報酬について
診療報酬は2024年改定(令和6年度)が基盤で、2025年はベースアップ(+2%)の特例対応が入り、医療機関の賃上げ支援が進んでいます。胃潰瘍は「特定疾患療養管理料」の対象で、慢性管理を評価。点数は1点=10円(2025年現在)。個別請求額は保険適用で3割負担の場合、数百〜数万円。詳細は医療機関や保険で異なり、厚生労働省の点数表を参照。
主な関連点数(令和6年改定ベース、2025年適用):項目点数内容・算定条件
| 項目 | 点数 | 内容・算定条件 |
|---|---|---|
| 初診料 | 288点 | 初回診療。胃潰瘍疑いで内視鏡前。 |
| 胃内視鏡検査 | 1,380点(上部消化管) | 診断・止血処置含む。鎮静剤使用で加算。 |
| ピロリ菌除菌療法 | 13,000点(1クール) | 3剤併用1週間。成功確認で加算なし。 |
| 特定疾患療養管理料 | 225点/月(診療所) | 胃潰瘍の継続管理(服薬・生活指導)。月2回まで。PPI長期処方で加算(特定疾患処方管理加算1: 100点/月)。 |
| 入院基本料(13対症) | 約5,000〜7,000点/日 | 消化器疾患入院。DPCで包括。短期滞在手術等基本料: 約20,000点。 |
| 内視鏡的止血術 | 2,000〜5,000点 | 出血時。クリップ使用で加算。 |
- 2025年の変更点: 全体+2%アップで、入院料・管理料が増額。急性期加算の経過措置(2025年5月まで)が6月以降に施設基準届け出で継続。胃潰瘍関連では、在宅支援強化で退院後管理料が増。
- 患者負担例: 外来治療(薬+検査)で初回約5,000〜10,000円(3割負担)。入院1週間で10〜20万円(高額療養費制度適用で軽減)。
- 注意: 点数は施設基準で変動。詳細は日本医療労働組合総連合会や厚労省サイトで確認を。
まとめ
- 治療のポイント: 薬+除菌で8週間以内の治癒が標準。入院は重症時のみ短期。
- 費用面: 保険適用で負担軽減。特定疾患管理で長期フォロー可能。
- 緊急時: 吐血・激痛で即救急。2025年は医療DX推進でオンライン相談も増えています。

