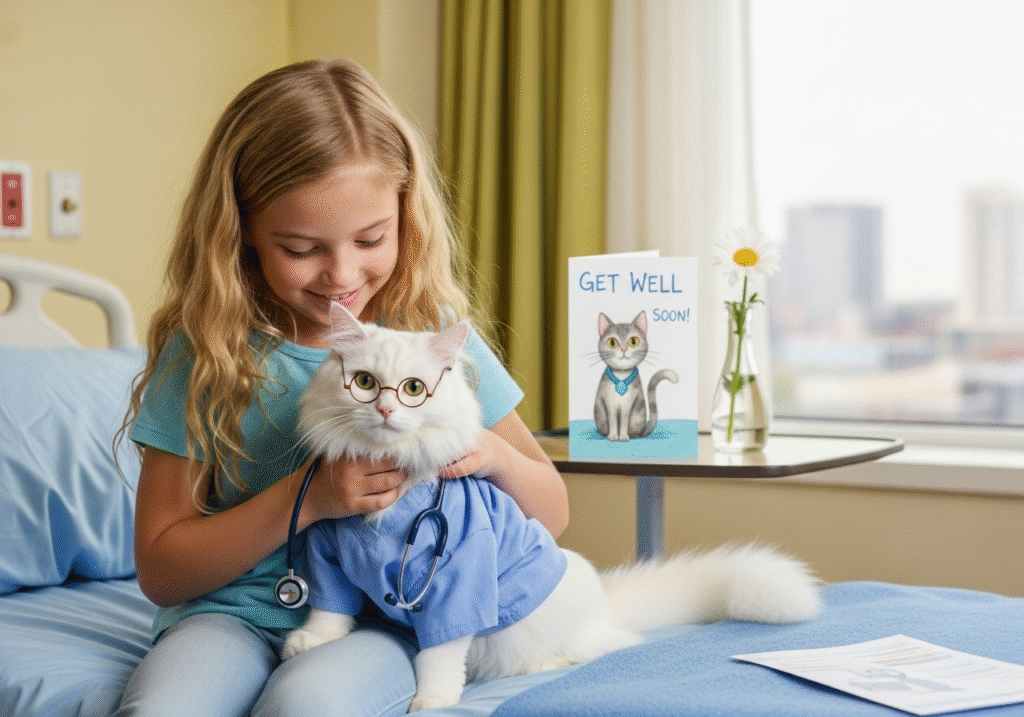
インフルエンザ(季節性)に感染した場合、あなたには会社を休む権利はあります。ただし、これは「法的強制力のある出勤禁止」ではなく、健康を守るための自主的な休養権と、会社の安全配慮義務に基づく配慮として認められます。2025年現在、労働基準法(労基法)でインフルエンザ特有の出勤停止は定められていませんが、感染拡大防止の観点から、多くの企業が学校保健安全法の基準を参考にルールを設けています。以下に、労基法の関連条文と企業ルールのポイントをまとめます。情報は厚生労働省・日本感染症学会のガイドラインおよび実務事例に基づきます。
1. インフルエンザで休む基本的な権利と期間
- 休む権利の根拠:
- 労働契約法第5条(安全配慮義務):会社は従業員の健康を守る義務があり、無理な出勤を強要するとパワーハラスメントや違法行為になる可能性。
- インフルエンザは発症後5日+解熱後2日(計7日程度)の安静が推奨(学校保健安全法施行規則第19条を参考)。これを超えても体調不良なら延長可。
- 法的強制力: 学校や保育園とは異なり、企業に自動的な「出勤停止」はありません。自主休養が基本ですが、会社が休養を命じると休業手当が発生します。
2. 労基法の関連条文と適用例
労基法はインフルエンザを「私傷病」として扱い、休みの賃金処理を規定。強制出勤は違法です。
| 条文 | 内容 | インフルエンザ適用例 |
|---|---|---|
| 第39条(年次有給休暇) | 勤続6ヶ月以上で年10日以上の有給休暇を付与。申請があれば拒否不可(業務繁忙でもNG)。 | 有給残があれば、インフル休養に使用可。本人が申請しない限り、会社が勝手に有給消化は違法。給与100%支給。 |
| 第26条(休業手当) | 会社都合の休業時は平均賃金の60%以上を支払う。 | 会社が出勤禁止を命じた場合(例: 感染防止のため)。インフル単独では「本人の都合」なので通常不要だが、命令時は義務。民法上100%が原則。 |
| 第119条(有給拒否禁止) | 有給申請を正当理由なく拒否すると罰則(30万円以下)。 | インフル理由での有給申請を「業務が忙しいから」と断れない。 |
- 欠勤扱い: 有給なし・申請なしの場合、無給。インフルは「私傷病欠勤」として扱われ、給与控除OK。
- 傷病手当金: 健康保険から支給(給与の2/3、4日目から)。インフルで連続4日以上休むと対象。
3. 企業ルールの例と実務対応
企業は就業規則で独自ルールを設け、感染防止を強化。2025年はテレワーク併用が増え、柔軟対応が主流。
| ルール例 | 内容 | メリット・注意点 |
|---|---|---|
| 出勤停止ルール(学校保健法準拠) | 発症後5日+解熱後2日を出勤禁止。診断書提出必須。 | 多くの企業(例: 大手製造業)が採用。休みは欠勤or有給。テレワーク可なら推奨。 |
| 病気休暇制度 | インフル特化の有給/無給休暇(例: 3日間無給)。 | 中小企業で増加。同一労働同一賃金法準拠でパートも対象。 |
| 報告・連絡ルール | 発熱時即電話/メール報告。家族感染時は予防待機。 | 感染拡大防止。未報告で懲戒の可能性(稀)。 |
| テレワーク併用 | 症状軽度なら在宅勤務OK。 | 2025年ガイドライン推奨。賃金全額支給。 |
- 企業対応の流れ(推奨):
- 症状報告 → 即医療機関受診・診断書入手。
- 休養申請 → 有給希望か確認(強制NG)。
- 期間中: 安静+感染防止(マスク・手洗い周知)。
- 復帰: 体調確認後(再発熱時は延長)。
4. 注意点とアドバイス
- 会社が休ませる権利: あります(安全配慮義務)。ただし、手当支払い義務が生じるので、自主休養を奨励。
- 有給強制はNG: 違法で罰則。残なしの社員に不公平を生む。
- 高リスク者(高齢・妊婦): 特別配慮(別室・優先休養)。
- 実例: 2024-2025シーズン、感染企業でクラスター発生→休養ルール強化の動き(厚労省報告)。
インフルは「ただの風邪」ではなく、重症化リスクあり。迷わず休んで回復優先を。会社ルール不明なら人事に相談を。

![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4e44f0c4.e0fc616f.4e44f0c5.16e6cd6f/?me_id=1209304&item_id=10092797&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fenergy%2Fcabinet%2Fnopoint%2Fp2setinhurkorona.jpg%3F_ex%3D240x240&s=240x240&t=picttext)

